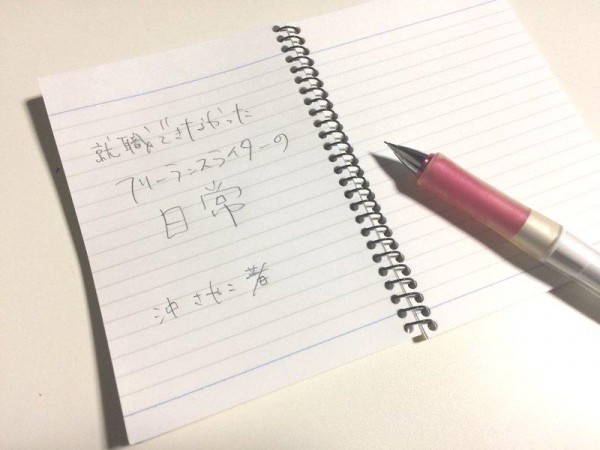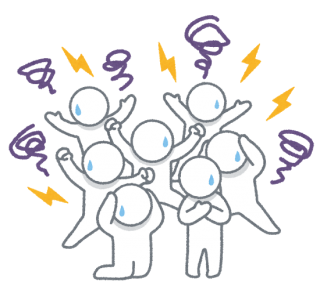就職できなかったフリーランスライターの日常(25)
就職できなかったフリーランスライターの日常(25)
3年目の落とし穴
前回のしょくふに第24回で「インタビューはなにが起こるかわからない」と書いた。本当になにが起こるかわからない。この10年間の経験で、特に印象に残っているアクシデント的エピソードを紹介する。(※お相手のご迷惑にならないように配慮したうえで書いています。性別もわからないようにしていますので、くれぐれも特定や詮索などなさらぬようお願い申し上げます)
+
ライター3年目くらいの時期、いまはなき某媒体でインタビューをした。
フリーランスのライターが行うインタビュー現場は、ほとんどその記事が載る媒体の編集者さんが付き添う。某媒体でインタビューをした際の編集者さんは、インタビュアーと一緒に会話へ参加するタイプの人だった。わたしは編集者経験がなく、そのタイプの編集者さんとお仕事をする経験もそれまで皆無だったため、その類の人がいらっしゃることをまったくもって知らなかった。
インタビュー中、アーティストの返答に対してわたしが口を開こうとすると、その編集者さんが「それってさあ」と話に介入した。無知なわたしはとにかくかなり動揺した。一言二言で終わるかと思いきや、編集者さんはインタビューの主導権を話す気配がない。おまけにその編集者さんはもともとそのアーティストと仲が良かった。たしかにインタビュー前の世間話も親しげではあったが、これがインタビュー中も続くなど思いもしなかった。編集者さんがタメ口で話し始めると、そのアーティストも顔が明るくなり、友達同士が喋るような朗らかな空気感が一気に花開いた。
突如の事態でペースは乱され、比べものにならないくらいいい空気を作られ、話も盛り上がり、「いや、それ質問するのもうちょっと後の予定だったんだけど!」「どうしよう、ここにいる方々全員にわたしが全然仕事できないやつだと思われてるかも……!」といった自尊心から生まれるショックにも襲われ、「わたしみたいなスキルのない人間、ここに必要ないじゃないか……」とどんどん落ち込み始める。すると編集者さんは話したいことを話し終えたのか、突如わたしに向かって道を譲るような仕草をした。
ええええ!? ここ!? ここでバトン返されるの!? 話題を連れ去るだけ連れ去って、さっきまでの道には戻ってきてくれないのね!? このあとどうつなげばいいのかしら!? と不安と動揺が津波のように押し寄せた。血の気が一気に引いた。インタビュイーの話をしっかり聞くことだけでも必死なのに、編集者さんの作った流れを汲んで話を進めなくてはならないぞ、どうする!? と、なんとか平常心を装って切り抜けていった――つもりだが全然誤魔化せてなかった。いつも以上に汗をかいて、天然パーマもさらにごわごわになっていたことだろう。
もちろん編集者さんもいい記事にするためのアシストとしてしていることだと思う。だが経験の少ない当時のわたしは、自分のペースだけで進められないこと、自分のペースを乱されることの耐性が一切ついてなかった。
最後までまったく口を挟まない方もいらっしゃれば、わたしのインタビューが終わったあとに気になった発言を掘り下げる方、インタビュー中に自分の訊きたいことを積極的に入れていく方、わたしの作るインタビューの流れのなかに違和感なく溶け込む方など、いろんなタイプの編集者さんが存在する。それを知る、洗礼的であり象徴的な出来事だった。
+
やはり同じくライター3年目くらいの時期、とあるアーティストにインタビューをした。過去の活動を振り返り、新作について話を聞き、初対面ながらに有意義なインタビューになった。その1ヶ月後、再びそのアーティストにインタビューをすることが決まった。インタビューの対象となる作品は既発曲のみが収録されていて、新曲の収録はない。過去のことはつい1ヶ月前にほとんど訊いてしまったばかりだ。なにを聞いたらいいんだろうか……? 悩みに悩んで、苦肉の策として思いついたのが「現在のことを訊こう」だった。
そして迎えた当日。現在の曲作りの進捗具合や、数ヶ月後には世にでることが決まっている楽曲に関する質問をいろいろとしてみても、アーティストの口は重く、歯切れが悪い。「そうか。まだ外には伝えられないことがたくさんあるんだろうな」と思い、これまでのミックスやマスタリング作業について質問をしてみた。だがこちらも不透明な返答ばかりだ。
インタビュアーは「お相手の話を聞くこと」が仕事なのに、まだまだ経験が浅かったわたしは「どうしよう、これではいい記事にならない。なんとかして言葉を引き出さなければ」という思考に支配される。するとどうなるか。とにかくいろいろ質問をすることに必死になってしまって、頭のなかはどんな質問をするかでいっぱい。お相手のことを見る余裕がなくなってくる。その時は気付かなかったが、後から考え直してみるとそのアーティストは終始あまり話したくなさそうにしていたのだ。
だがハイパーパニックな未熟者はそんなことに気付かない。お相手は空気の読めないわたしにどんどん苛立ちを募らせ、しまいには腕を組み、目をそらし、ソファにもたれかかり、声のトーンも低くなり、すべて吐き捨てるような口調になり、顔面には嫌悪感が露になった。とうとうここで気付いた。「怒らせてしまった」と。
1時間予定のインタビューは40分強で切り上げることになった。わたしが気遅れした態度を見せてお相手が「やりすぎてしまったな」と後悔することは避けたかったので、最後までお相手がお怒りであることに気付かないふりをした。用意された飲み物を飲みながら世間話を振ると、お相手は引きつった顔をしながら鼻で笑った。そりゃそうだ、目の前の人間が最後まで空気読めないんだから。コップをテーブルに置くや否やアーティストスタッフさんが早々とわたしと編集者さんを部屋から追いやった。扉の閉まった音が、いつもより大きく感じた。
数年後、そのアーティストのインタビューを読んでみると、わたしがインタビューをした時期はスランプだったと語っていた。そんななかで現在の曲作りのことなどを質問してくるライター、不愉快極まりない。そのアーティストの情報を見かけるたびに、あの時の失礼を詫びたい気持ちでいっぱいになる。
それからというもの、取材に不安要素が少しでもある場合は編集者さんに相談するようにしている。三人寄れば文殊の知恵とはよく言ったもので、ふたりであってもひとりでは思いつかない打開策が出てくるものだ。ちょっとずつ仕事に慣れてきていて、だけどまだまだわからないこともたくさんあるという「3年目」くらいに大きな落とし穴があるのだろう。苦い思い出が今のわたしを作っている。古傷が疼くことも、生きていくうえで重要なのだ。
note:https://note.mu/sayakooki
Twitter:https://twitter.com/s_o_518